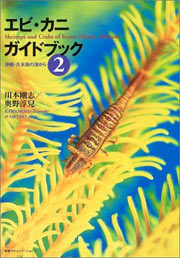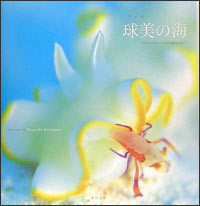第65回
先日、北側のポイントで、ハコヤンに出会った!!
「ハコヤン」と言うのは、ハコベラとヤンセンニシキベラの雑種と思われる個体で、毎年、新しい雑種を見るものだから僕が勝手に簡略化して呼んでいる2つのベラの雑種の事です。
何か、ヤンキーぽい(?)、古き良き時代を感じさせる言葉に聞こえるのです・・・・・。
今年の8月号に掲載したハコヤンは相変わらず、別のポイントで観察しているのですが、ある別のポイントにいたのを、たまたま見つけたのです。
・・・・・・・で、フリーでカメラを持って入っていたので撮影を始めたのですが、プレビューを見ながらある事に気が付きました。

見た目より体色が濃いのです。見た目は、今年の夏に見つけたこんな感じの子なんだけれども・・・・・

写真で撮ると、明らかに濃いのです。・・・・・・、逆なら、解るんです。
ストロボを当てて青被りしてた色彩が表れたのなら・・・・、つまり濃い体色が明るくなったのなら理解できるんですが、「明るく見える体色が、光を当てて濃くなるなんて信じられな〜い!?」・・・・・なんです。
20年前、Nembrotha livingstonei というリュウグウウミウシの仲間をフイルムカメラで撮影した時に、黒い身体に鮮明な赤色の小さな斑点がいくつもあるウミウシを撮影したはずなのですが見当たらない。
当時は、ライトを当てずに撮影をしてた僕はフイルムを無くしてしまったのではと思いましたが、よく確認すると、ポジ内に茶色の身体に濁った赤茶色の小さな斑点があるウミウシを発見しました。
次の機会に再度撮ってみるとそれであった事が判明し、海中生物の持つ色彩の濃さや淡さにとても驚いたものでした。
・・・・・でも、逆は無しでしょう〜!?しかも、魚だし・・・・。
ただ、その種が雑種などではなく、1つの種として確立するまでには、生息していく環境などを考慮して体色も形成されていったのだと思うので、その遺伝子情報はもちろん、その環境や諸々の条件で、例え、同じ場所にいる魚の色が同じような赤色に見えたとしても、別種である限り、その生物の本来持つ色彩の濃さや淡さや質感の関係で、人工ライトを当ててみると、それは、まったく違った色彩に変化するかもしれない可能性は当然あると思うのです。
その種は(生物)の遺伝子は、決して、ダイバーからライトやストロボを当てられる事を考慮して、身体の色彩を形成しないでしょうから!?
・・・・・話が理屈っぽくなってしまいました。・・・・・・でも、逆はないと思うだよなぁあ〜!?

川本 剛志
1965年4月3日生まれ
福岡県出身
ガイド会所属
久米島でダイビングサービスを営むかたわら、ライフワークである、冬に訪れるザトウクジラや各種の魚類、サンゴ、ウミウシ、甲殻類の生態を写真に収め続けている。多数の図鑑雑誌に写真を提供し、エビ・カニガイドブック2-沖縄・久米島の海から-等の著作を持つ。
沖縄・久米島
DIVE ESTIVANT
〒901-3108
沖縄県島尻郡久米島町比嘉160-69
Tel:098-985-7150
Fax:098-985-7151
川本氏へメールで申し込めば、代金先払い&送料着払いで送ってもらえるそうです。サインが欲しければこっちだね!(笑)
BY 編集部
バックナンバー
- 2016.7:第108回
- 2016.6:第107回
- 2016.5:第106回
- 2016.4:第105回
- 2016.3:第104回
- 2016.2:第103回
- 2015.11:第102回
- 2015.10:第101回
- 2015.9:第100回
- 2015.7:第99回
- 2015.6:第98回
- 2015.5:第97回
- 2015.4:第96回
- 2015.2:第95回
- 2015.1:第94回
- 2014.12:第93回
- 2014.11:第92回
- 2014.10:第91回
- 2014.9:第90回
- 2014.8:第89回
- 2014.7:第88回
- 2014.5:第87回
- 2014.4:第86回
- 2014.2:第85回
ガイドのつぶやき
- 三浦半島・葉山から
- 真鶴半島・湯河原から
- 伊豆半島・伊東から
- 伊豆半島・川奈から
- 伊豆半島・伊豆海洋公園から
- 伊豆半島・大瀬崎から
- 伊豆半島・平沢/静浦から
- 伊豆諸島・八丈島から
- 静岡・三保から
- 紀伊半島・尾鷲から
- 和歌山・串本/古座から
- 高知・沖の島から
- 鹿児島・屋久島から
- 沖縄・本島から
- 沖縄・久米島から
- 沖縄・西表島から